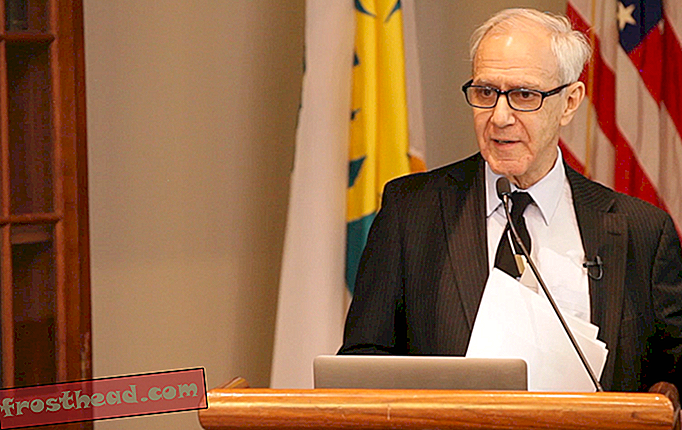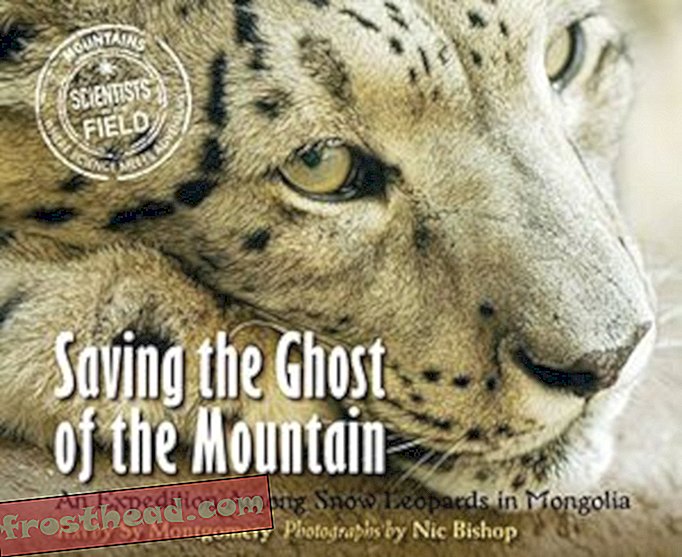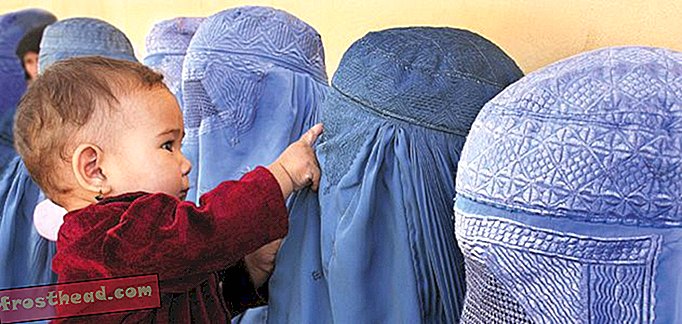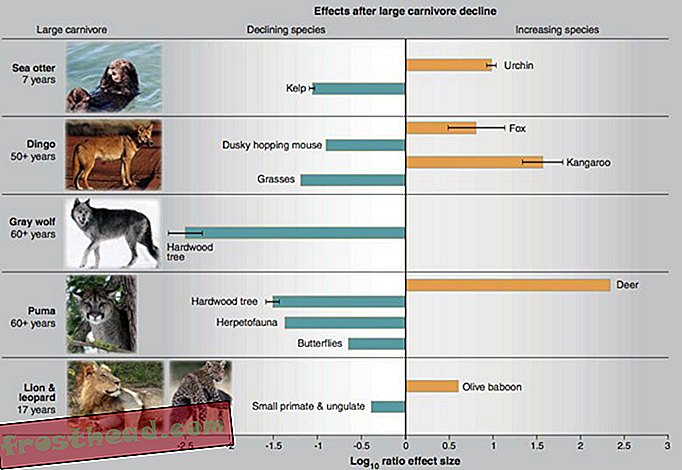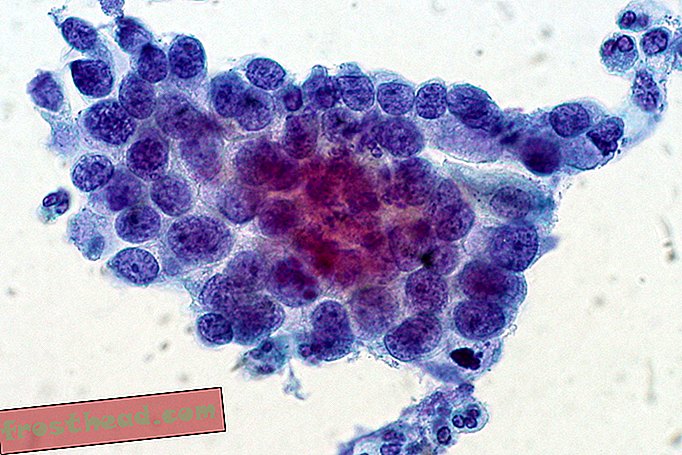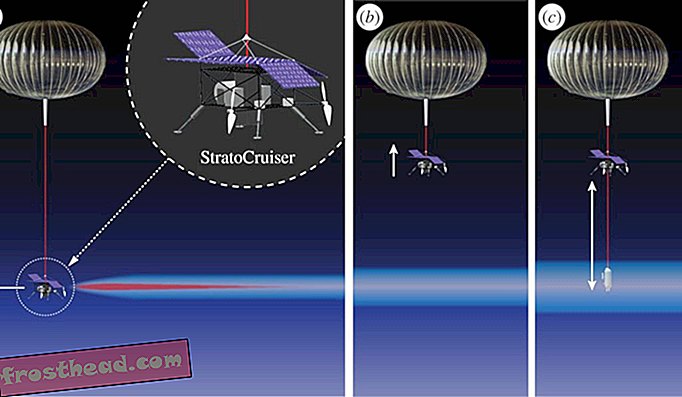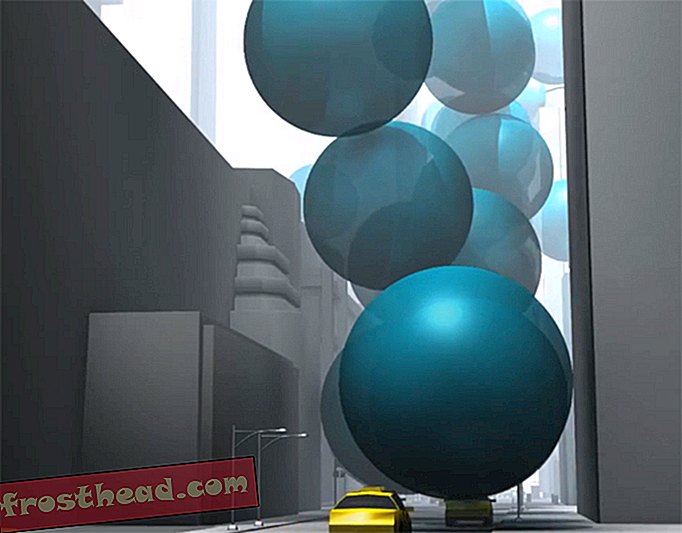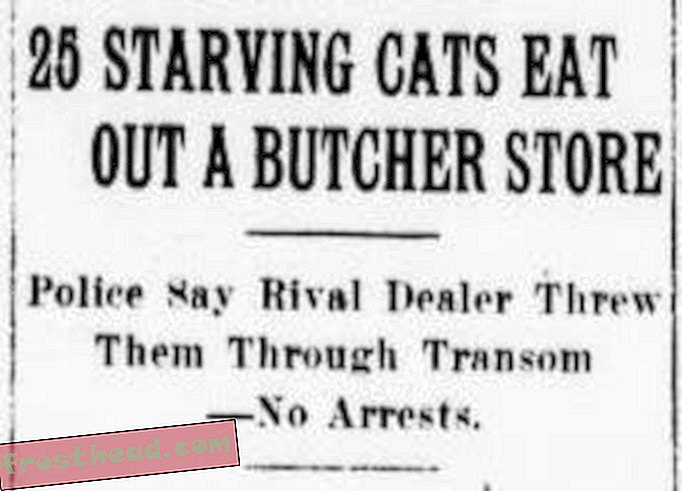ほぼ毎冬、日本アルプスのafter訪湖が凍った後、雄の神である竹南方が氷を渡り、神社の雌の神であるkat留を訪れ、御wat渡として知られる尾根を形成します。 少なくとも、湖のほとりに住む司祭たちはそう信じていました。 水が凍ったとき、彼らは尾根に敬意を表して浄化の儀式とお祝いを行い、その方向と開始場所を使用して、翌年の収穫と降雨を予測します。
司祭たちは1443年に始まったこの出来事の記録を保持し、不注意に気候条件の膨大なデータセットを作成しました。 現在、ヨーク大学の生物学者であるサプナ・シャルマとウィスコンシン大学の陸水学者であるジョン・J・マグナソンは、そのデータをフィンランドのトルン川の春の氷解の記録と組み合わせて、内陸水に対する気候変動の影響を理解しました。
「これらのデータはユニークです」とシャルマはプレスリリースで述べています。 「それらは、気候変動が議論のトピックでさえあるかなり前に、氷の出来事を何世紀も何年も見て、記録する人間によって集められました。」
本日、Scientific Reportsで発表されたこの研究は、S訪湖の年間凍結日が非常にゆっくりと変化し、10年ごとに約0.19日早く変化したことを示しています。 しかし、産業革命が始まると、凍結日の変更は劇的に急増し始め、10年ごとに約4.6日シフトしました。
18世紀後半に産業革命が始まる前に、湖は99%凍結しました。1800年以前の3世紀には3回凍結するだけでした。現在、S訪湖は半分の時間で完全に凍結しています。 過去10年間で、湖は5回凍結できませんでした、とナショナルジオグラフィックのリサボレは書いています
1693年、フィンランドの商人Olof Ahlbomは、北極海からバルト海に流れるスウェーデンとフィンランドの国境の一部であるトルネ川で氷が解けた日時の記録を取り始めました。 戦争により1715年から1721年の間に記録保持が中断されましたが、それ以外の場合は記録がオブザーバーによって維持されています。
TorneのデータはLake訪湖のものと似ています。 1693年から1799年の間に非常に暖かい年が4回しかなかったので、4月に氷が解け、過去10年間で5回になりました。 「2つの水域は世界の半分離れており、互いに大きく異なっていますが、氷の季節性の一般的なパターンは両方のシステムで類似しています」とマグナソンはプレスリリースで述べています
Borreによれば、この調査結果は、北大西洋振動やエルニーニョ南方振動など、世界中の湖や川の氷の被覆に影響を与える気候サイクルの変化を特定した他の研究にも当てはまります。 しかし、この研究の最大の発見は、異常な記録に気候変動に関するより質の高いデータが存在する可能性があることです。
「私にとって非常に興味深いのは、人間の直接観察に基づいて、世界最長の氷の記録を分析に含めることができたことです」とマグナソンはボアに語ります。 「世界のさまざまな地域の2つの非常に異なる淡水システムからのこのような長い記録が同じ一般的なパターンを示すことは、私たちの重要な発見の1つです。