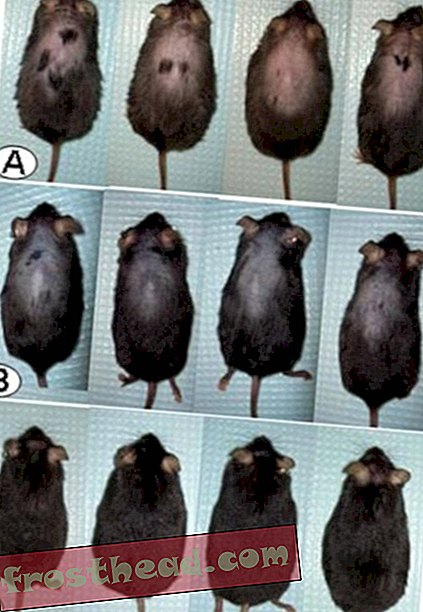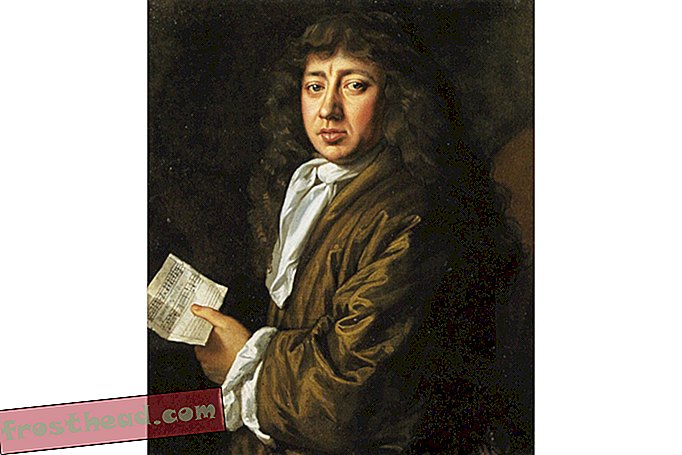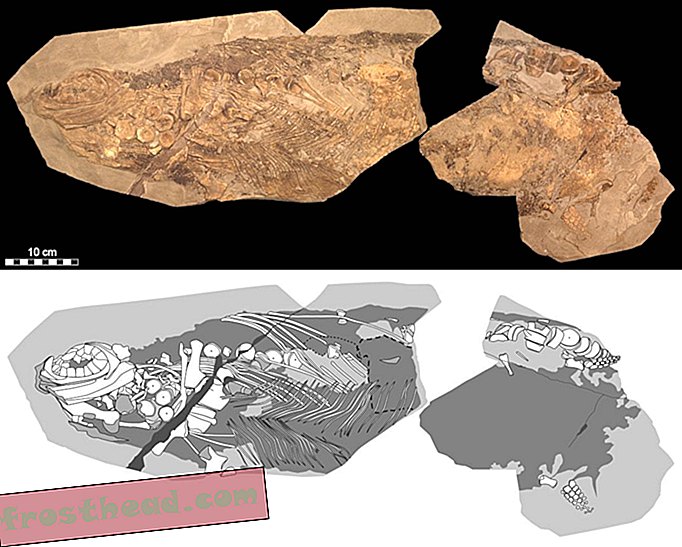摩擦マッチは、人々に火を迅速かつ効率的に点火する前例のない能力を与え、国内の取り決めを変更し、より原始的な手段を使用して火を点火しようとする時間を削減しました。 しかし、彼らはまた、マッチメーカーに前例のない苦痛をもたらしました。最初の摩擦マッチのいくつかで使用された物質の1つは、白リンでした。 それに長時間さらされたことで、多くの労働者は恐ろしい「骨付き顎」を手に入れました。
関連性のあるコンテンツ
- ヒ素と古い味がビクトリア朝の壁紙を致命的にした
- 国際女性の日を刺激したアメリカの衣服労働者
- これらの女性記者は、その日の最も重要なスクープを取得するために潜入しました
今日の科学史によると、ジョン・ウォーカーというイギリスの薬剤師が1826年にこの日に偶然にマッチを発明しました。 彼は銃で使用されるかもしれない実験的なペーストに取り組んでいた。 彼は、ペーストに含まれる物質を混ぜるために使用していた木製の器具をこすり落としたときに突破口を開きました。
The Pharmaceutical Journalの Andrew Haynes氏は、少しの作業で、「硫化アンチモン、塩素酸カリウム、アラビアゴムで作られた可燃性ペーストを硫黄でコーティングされた段ボールストリップに浸漬しました」と書いています。 1827年4月に地元の人々が急いで離陸しました。
ウォーカーは発明の特許を一度も取得していないと、ヘインズは書いています。「燃焼する硫黄コーティングが時々床から落ち、床やユーザーの衣服に損傷を与える可能性があるからです。」 BBCに、だから彼がそうしなかった理由は少し不明瞭です。 彼の発明はロンドンのサミュエルジョーンズによってすぐにコピーされ、1829年に「ルシファー」の販売を開始しました。
これらの新しいデバイスでの実験により、白リンを含む最初のマッチが作成されました。これはすぐにコピーされました。 ブリタニカ百科事典によると、試合の進歩は1830年代から1840年代まで続いた。
マッチメイキングはイギリス全土で一般的な取引になりました。 「何百もの工場が全国に広がっていた」とKristina KillgroveはMental Flossに書いている。 「1日12〜16時間、労働者は処理済み木材をリン調合液に浸し、乾燥させて棒をマッチに切りました。」
Killgroveによると、19世紀および20世紀における他の多くの低賃金で退屈な工場の仕事と同様に、マッチメーカーは主に女性と子供でした。 「この業界の従業員の半分は、10代にも達していない子供でした。 cr屈で暗い工場で屋内で長時間働いている間、これらの子供たちは結核にかかり、くる病になるリスクがあり、マッチスティックの作成には特定のリスクがありました:顎の骨。
この恐ろしくて衰弱する状態は、工場での長い時間の間に白リンの煙を吸い込むことによって引き起こされました。 「リンの煙にさらされた人のおよそ11パーセントが、平均して、最初の暴露から約5年後に「顎骨」を発症しました」とKillgroveは書いています。
この状態により、顎の骨が死に、歯が虫歯になり、ひどい苦痛が生じ、時には顎が失われます。 フォッシージョーは、長期にわたる白リン曝露の唯一の副作用からは程遠いものでしたが、マッチ植物の工業化学物質によって引き起こされる苦しみの目に見えるシンボルになりました。 1892年までに、雑誌Victorian Studiesの Lowell J. Satreが、新聞はマッチワーカーの苦境を調査していました。
The Starのロンドンの記者は、救世軍の試合工場で働いていた、あごのあごの犠牲者を訪問しました。 ミセス・フリートと名付けられたこの女性は、「会社で5年間働いた後に病気にかかったことを明らかにした」とサトレは書いている。 「歯と顎の痛みを訴えた後、彼女は家に帰り、4本の歯を抜いて、顎の骨の一部を失い、病気の耐え難い痛みに苦しみました。」彼女の頬はとてもひどかったので、彼女の家族は耐えられなかった。
この後、彼女は試合会社から手放され、数ヶ月間彼女に支払いました。 その後、彼女は別の仕事を得ることができなかった。他のマッチ会社が彼女を雇うことはなかった、とサトレは書いている。 「歴史的記録は、明らかな身体的損傷と状態の社会的不名誉のために、しばしば顎の痛みの患者をハンセン病の人々と比較します」とKillgroveは書いています。
最終的にマッチメーカーは試合で白リンの使用をやめ、1910年に米国で禁止されました。